こんにちは。cocoです。
今回は入学して初年度の1年次のスクーリングについて、実際に受講した体験から気づいたことなんかを書いていこうと思います。
1年次のスクーリングの日程

1年次に行われるスクーリングは
✓春(もしくは夏・秋)に行われる概論スクーリング
✓2月~3月にある基礎看護学実習後の実習スクーリング
がありました。
基礎看護学実習スクーリングは、実習に参加した人だけのスクーリングでした。なので実習参加条件をクリアできなかった人は、その時点で留年が確定になりました。
春(もしくは夏・秋)の概論スクーリングは2科目を3日間で行っていました。
例えば1クールは
・1日目 AM母性 PM小児
・2日目 AM小児 PM母性
・3日目 AM母性 PM小児 最終で修了試験
という感じです。
ほとんどが土日で行われるため、
普段は仕事をしていて、休みの日に大学へ来て勉強している学生が多かったです。
なので、
✓疲れている通信看護学生の負担を軽減する授業構成
✓いかに興味をもって授業を聞いてもらうには、どうすればいいか
✓どうやって理解してもらうか
と先生方も真剣に授業構成を考えてくれていました。
スクーリングで困ったこと(個人的)
さて、そのスクーリングですが
プレカレッジに参加してその時に仲良くなった人や、最初の席で近くになって話をするようになったりして、近くの席で講義を受けるようになることがほとんどでした。
私も最初は特定の人たちと近くに座って講義を受けていました。
そして休み時間はグループのようになり、お菓子の交換会になりました。
これが面倒くさがりな私には最初の難関でした。
(途中から何を買っていこうかと考えることが面倒になり…)
私は春スクーリングを選択したので、6月には概論スクーリングは全て終わったのですが、
「これで会わなくていいのか」と少しほっとしたのは事実です。
(みんなでワイワイすることで看護学生気分も存分に味わえますが)
3日×➂=9日間
こうやってみるとすごく少ない日数なのですが、それでも人とずっと一緒にいると自分にとってはストレスになるんだなと実感しました。
通信制看護学生生活での友人関係について考える
先生方は入学式の時から「友達を作って励ましあえば勉強のやる気になる」ということで、友達作りを推奨しています。
私も最初はプレカレッジや入学式で席が近くになった人と連絡先を交換をしたりしてたので、スクーリングの講義の時にも一緒にいました。
しかし、そのスタイルが自分には合わないと思うようになりました。
なのでスクーリング終了後きちんと断りをいれてから、自分1人で勉強するようにしました。
友人がいるのと、勉強を頑張れるのは別の話
状況を報告しあうような関係の人がいると「あの人、もうここまで進んでる。私も頑張らなきゃ」と焦ります。今日は疲れていたけど、もう少し勉強しようと確かに思ったこともありました。
しかし、その分愚痴や不平・不満もついてきていました。これが私にとっては苦痛でした。
自分で計画立てて勉強していける自信も正直あったので、そのほうが自分にとっていいと思い実行しました。
勉強が思う様に進まない時も、もちろんありました。
そういう時こそ「もしかしたらあの人たちは勉強しているかもしれない。負けてたまるか」と思ってやる気にしていました。(勝ち負けではないのですが)
2年次になってからの実習やスクーリングでは知っている人も増えてくるし、特に友人がいなくて困ったということはありませんでした。
自分にとって適切な環境はどういう環境かを考える
友達が必要・必要でないというのではなく、自分がどういう環境だと勉強しやすいかを考えて、その環境を自分で作ることが大事だと思います。
愚痴を言い合って解消したいのなら
同じようなタイプの人と愚痴を言いながら勉強するほうが、お互い効果的かもしれません。
私のように「とにかく自分のペースで自己責任でやりたい」ならそういう環境をつくる方が勉強が進むと思います。
おわりに
自己責任でやるということは、「他人に期待しない」ということであり、これは仕事をする上でも持っておきたい心構えだと思っています。
特に遠方から初めてスクーリングに参加するというかたは、知り合いもいないので不安を感じるかもしれません。
しかし、みんな同じような環境でスタートしているといっていいと思います。
それよりも、「自分にとっていい環境で勉強するには?」ということをまず1番に考えて、学生生活を乗り切ってくださいね。
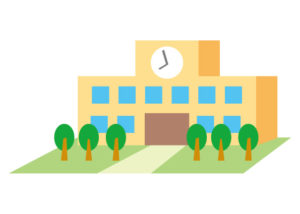
よかったら参考にしてみてください。


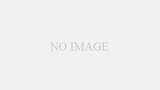
コメント