こんにちは。cocoです。
今回は各論実習でも実習先によって準備などの差が大きかった小児看護学実習について書いていこうと思います。
小児看護学実習の準備について

小児看護学の実習は、母性に次いで実習先の違いが大きいと思いました。
例えば、事前に誓約書を記入する実習先もあれば、使用している名札(クリップや安全ピンでとめるタイプ)は子どもに危険なので、布製の名札を用意し白衣に縫いつけておくといった準備が必要な実習先もありました。
また、事前に配属される病棟(何科なのか)を教えてくれる実習先や、行ってみないと分からないといった実習先もありました。
準備が必要な実習先は、その準備が出来ていないと実習させてもらえないと思っておいた方がいいです。
いくら見学実習とは言え、自分の意思を上手に伝えることが困難な年齢の患児もいます。
また患児の家族に余計な心配をさせないように努めるのも、実習生の大きな役割の1つであると思います。
では具体的にどんな実習だったのか、私が実習した病院での流れをお伝えしようと思います。
これは1つの例として参考にしてくださいね。
私が実習した小児科実習の流れ

私が実習した病棟では、病院前の指定場所でメンバーが揃うのを待ちました。
みんな時間より少し早めに到着しており、少し話する時間もありました。
(患者さんや家族の方も来院されるので邪魔にならない様、また声の大きさも配慮しました)
時間になると最初に看護部長のところへ全員で挨拶に行きました。
そのあと更衣室で着替えてからまた集合し、順番に各実習の配属先へ案内されました。
そして実習先の病棟でのオリエンテーションがありました。
オリエンテーション後は「見学できる処置やケアがあると教えてもらえ、見学する」という実習方法だったので、他の実習生とペアになり見学しました。
記録に関しては、実習先の指導者の方から「空いた時間に記録していいですので」と言ってもらえたので、時間が空いた時に少し書いていました。
ただ、いつ見学に呼ばれるか分からないので、ナースステーションで待機してカルテを見させてもらったりしました。ケアが少ない時は患児とのコミュニケーションのために病室にいる時間もありました。
勝手に病室に入ってはいけないという実習先もあるようですが、私が実習したところは比較的病態が落ち着いて、看護学生が受け持ちしたこともある患児を教えてもらえました。
そしてコミュニケーションを図ってきてもいいいですよと言われたら、患児やその家族の方と会話することが出来ました。
ただ一つヒヤヒヤしたのが、一緒に見学していたメンバーが敬語が使えない人だったことです。
指導担当者は敬語が使えない通信制看護学生の経験があるのか、慣れた様子で怒ることもなかったです。
(もう諦めているのかもしれませんが…毎回何人かはいるのでしょうね…)
しかし実習指導者の方以外の看護師さん(処置やケアの見学をさせてもらう時にいた看護師さん)は
「なに!?この馴れ馴れしい話し方!友達じゃないんだから!!」
という感じで表情が引きつっていました。
(そのひとのフレンドりーなキャラと言えばそれまでですが、キャラは封印したほうがいいでしょう。)
恐らく機嫌を損ねたのでしょう。そのメンバーが質問をしたのですが、答えてもらえないこともありました。
いくら担当の看護師さんが明らかに年下の看護師さんでも、自分の勤務先ではないので敬意をもって接するのは必要かなと思います。(無視はダメだと思いますが…。)
話が逸れましたが(;’∀’)
事前に配属される実習病棟にどんな疾患の患児いるか、また疾患について事前学習をしてくるように通知がある実習先もあります。その場合はその範囲を予習しておけばいいと思います。
事前に分からない場合であれば、国試によく出そうなメジャーな疾患を勉強しておくといいと思います。
また国試対策だけでなく家族看護などについても大いに勉強できるので、事前に予習しておくことをお勧めします。
小児科実習では小児の発達段階を見ておく
小児看護学実習で大事なのは発達段階です。
これは事前に一通り看護師国家試験内容を見ておくと役に立ちます。
「どれくらいの年齢で何ができるのか」「この患児は〇歳だから一般的には○○ができる頃かな?」と知識と照らし合わせて見学することで、実際に看護師国家試験に出題された時に「ああ、実習で見学した」と紐づけて記憶をたどることができるからです。
ケアを中心に見ていく実習であれば、なおさら「この子は何歳だろう?どこまで自分でできる?どう関わって成長を促す看護をしている?」と考えたり、指導者の方に聞きながら実習していくことをお勧めします。
おわりに
実習はちょうど梅雨の明けた熱い日にすることがほとんどです。
移動時も辛いと感じることも多いと思いますが、身体に気をつけて実習を乗り切ってくださいね。
よかったら参考にしてみてください。

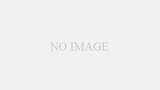

コメント